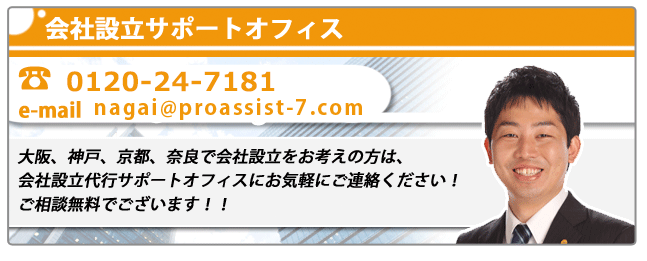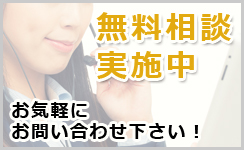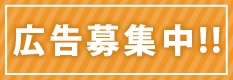独占禁止法について
独占禁止法とは
独占禁止法は、経済全体がうまく回るようにするための企業活動の基本的ルールを定めた法律です。
正式には、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」といいます。
独占禁止法は、競争の妨げになる独占行為・不当な取引制限・不公正な取引方法などを禁止するものです。
例えば、テレビを製作するメーカーが集まって液晶テレビの価格を20万円にするという取り決め(価格協定)がなされると、本来行われるべき価格競争が失われてしまいます。
そのため、このような価格協定行為は独占禁止法によって規制されているのです。
同様の理由で入札談合も規制されています。
また、特定の事業者と取引をしない取引拒絶や、同じ製品の価格を場所や人によって差別する行為についても市場における自由な競争を損なう危険があります。
そのため、不公正な取引方法として禁止されています。
不公正な取引に該当する行為
①特定の事業者と取引をしない、させない(取引拒絶)
②同じ製品の価格を場所や人によって差別すること(差別価格)
③不当に安い価格で販売すること(不当廉売)
④買い占めなど不当に高い価格で購入すること
⑤虚偽、誇大広告、過大な景品により顧客を誘引すること
⑥他の製品と抱き合わせて販売すること
⑦競争者と取引しないことを条件として相手方と取引すること
⑧商品の販売価格を相手方に自由に決めさせないこと
⑨相手方の取引先や販売地域を拘束すること
⑩自己の優越した地位を利用して相手方に不利益な条件をつけること
⑪競争相手の取引を妨害したり、不利益となる行為を誘引・そそのかし・強制すること
違反者は罰則を負うこともある
①民事上の損害賠償責任
独占禁止法違反行為によって損害が生じた場合、被害者から損害賠償請求を受けることがあります。
この賠償責任は、故意や不注意がなくても責任を負う無過失責任とされていますので注意が必要です。
②行政処分
事業者が独占禁止法に違反すると、行政上の処分として、公正取引委員会から排除措置命令という処分が下されます。
排除措置命令に従わないと刑事責任を問われます。
また、私的独占やカルテルといった独占禁止法違反行為によって得た利益を没収するため、課徴金納付命令という行政処分を下されます。
課徴金の金額は違反行為を繰り返す事業者ほど多く課せられる仕組みになっています。
③刑事罰
違法行為によって刑事罰の程度は異なってきますが、私的独占または不当な取引制限をした者に対しては、5年以下の懲役または500万円以下の罰金が課されます。
★大阪の会社設立なら会社設立代行大阪サポートオフィスにお任せ下さい!
★大阪の会社設立以外にも、神戸、京都、奈良、和歌山などの近畿圏内の会社設立にも対応しております!